バレンタインの由来が怖い?処刑された司教とバレンタインデー発足の思惑
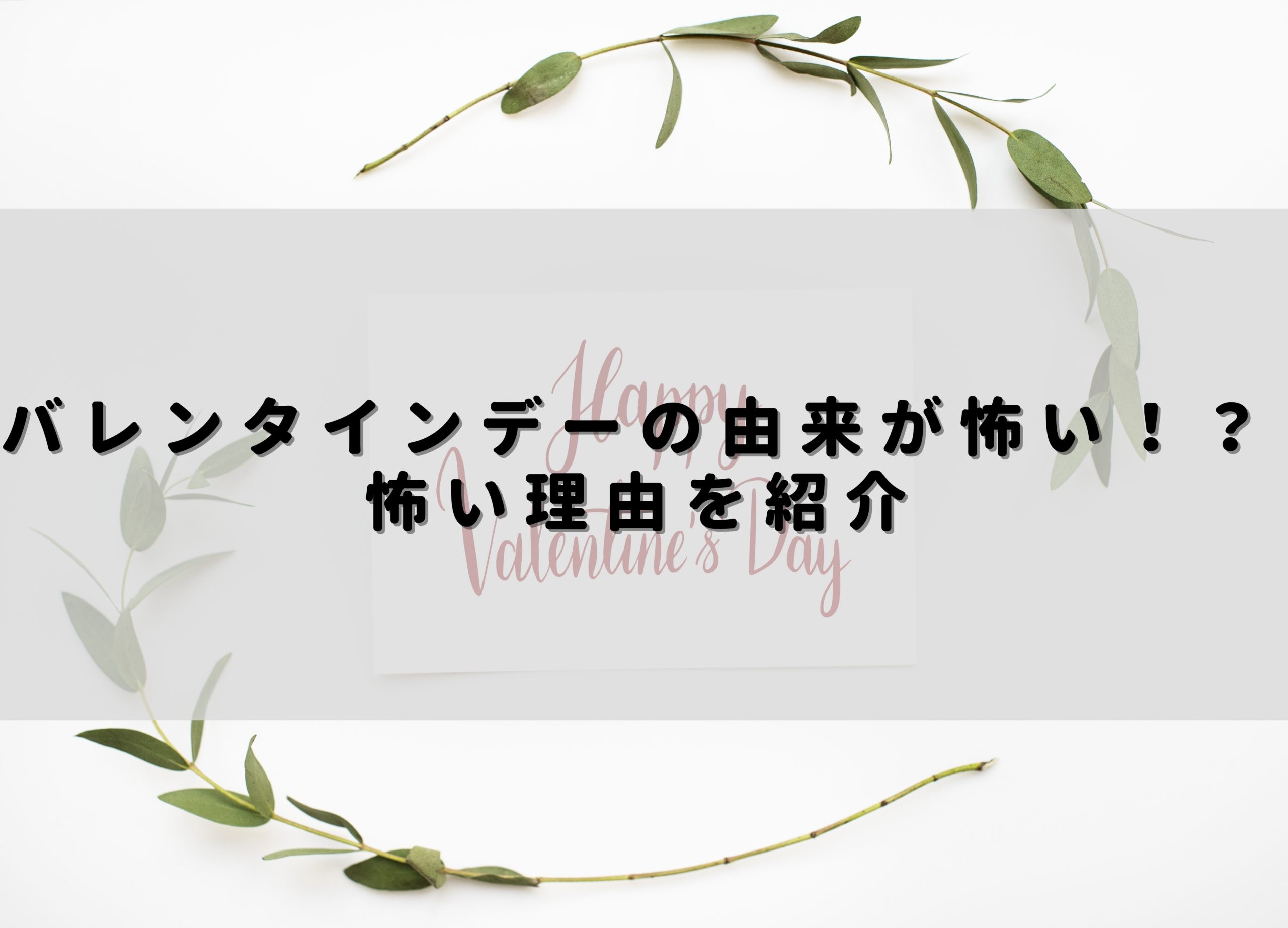
今ではすっかりイベント行事として浸透しているバレンタインですが、実際に調べてみたら、由来や起源が意外と怖いものでした。
そして日本でのバレンタインは、女性から男性へチョコレートを贈るという日本独自の文化が根付いており、ネット上では「チョコレート会社の陰謀」とも呼ばれていますが、日本のバレンタインデーの始まりはどういったものなのか、いつから女性から男性へチョコレートを贈るようになったのかも調べてみました。
この記事では、バレンタインの由来や起源が怖い理由と、日本のバレンタインデーの始まりについて紹介していきたいと思います。
バレンタインの由来が怖い理由
ここでは、バレンタインおよびバレンタインデーの由来が怖い理由について、ポイントごとに紹介していきます。
※バレンタインの由来については諸説あるので、有力であると思われる情報を基に作成しています。
怖い理由その①バレンタインデーの2月14日は処刑された司祭の命日

バレンタインという名称は、西暦3世紀のローマ帝国時代、当時のローマ皇帝クラディウス2世から迫害を受け殉教したキリスト教の司祭「ウァレンティヌス(バレンタイン)」に由来するとされています。
そしてバレンタインデーとは、ウァレンティヌスが処刑された命日にあたるんだそうです。
処刑された人の命日がバレンタインの由来って怖いですよね。
2月14日がバレンタインデーと呼ばれるようになった理由はわかりましたね。
ではそもそもなぜバレンタインデーができたのか、起源について紹介していくのですが、
バレンタインデーの起源に入る前に、バレンタインデーが始まる前に行われていた「ルペルカリア祭」について知っておく必要があります。
怖い理由その②くじ引きでカップル成立?!ルペルカリア祭

元々2月14日は女神である「ユーノー」の祝日とされており、その翌日2月15日からは「ルペルカリア祭」という豊作を祈願する祭りが開催されていたようです。
当時ローマ帝国では、男性と女性は住処を別々にして生活していました。
ルペルカリア祭の前日2月14日(つまり今のバレンタインデー)に、女性が自身の名前を書いた紙を桶の中に入れ、翌日にその桶に入った紙を男性が引くことで、その二人は祭の間、パートナーとして一緒にいることを定められていたそうです。
この祭をきっかけに結婚する人が増え、ルペルカリア祭は、男女を結びつけるというところから、今日のバレンタインデーのような「恋人の日」という認識になったとされています。
お互い良いと思えるならいいかもだけど、くじ引きで決められた相手と一緒に過ごさなくちゃいけないのってちょっと怖いですね。
怖い理由その③娘を鞭で打つ?!ルぺルカリア祭もう一つの側面
ルペルカリア祭は、前述した豊作を祈願するほかに、多産祈願と浄化も目的としています。
ヤギと犬をいけにえとしてささげる儀式の後、腰布をまとった若い男たちが若い娘たちを生贄にした犬や羊の皮で作った鞭(むち)で打ちながら走り回り、この鞭に打たれると子宝に恵まれるとされていたので、娘たちは鞭に打たれるためにすすんで肩を露にしていた、という言い伝えが残っています。
少し違うかもしれませんが獅子舞のようなものだったのでしょうか?
それにしても鞭で打たれるなんて今では考えられないですよね。
このルペルカリア祭が、バレンタインデーが始まる前に行われていた祭りです。
ここからバレンタインデーの起源に入っていきたいと思います。
怖い理由その④バレンタインの起源!祭の廃止とバレンタインデー発足の思惑

時は流れ、5世紀になると、村の風紀が乱れることと、異教徒の神が混在する祭りを排除したいと考えるローマ教会とローマ教皇ゲラシウス1世により、ルぺルカリア祭は廃止されます。
しかし、民からの反発もあり、容易に廃止することはできませんでした。
教会は祭りに何かキリスト教に由来する理由をつける必要があると考え、新たな祭りがつくられることになります。
そこで上がったのが、キリスト教の司祭「ウァレンティヌス」です。
司祭の名を借りてバレンタインデー発足
西暦3世紀のローマ帝国時代、「兵士が妻や恋人を故郷に残していると士気が下がる」という理由から、兵士たちの婚姻は禁止されていました。
婚姻の禁止に悲しむ兵士たちを不憫に思ったキリスト教の司祭「ウァレンティヌス(バレンタイン)」は、禁令に背いてこっそり内緒で結婚式を執り行っていました。
しかしそれが皇帝の耳に入り、ウァレンティヌスを捕らえ結婚式を中止するよう忠告しましたが、ウァレンティヌスは忠告に従わず、2月14日に処刑されてしまいます。
教会は、このウァレンティヌス司教の名を借りて、バレンタインデーを発足させました。
バレンタインデーはルペルカリア祭で行われていた男女を結びつけるという特色を色濃く残しながらも、 異教徒にも受け入れられる形で祭をキリスト教化させ、異教徒の改宗をも目論んだのでは?とも考えられています。
これがバレンタインデーの起源になります。
バレンタインがキリスト教の祭りになったのはこの頃からだったんですね。
司祭の死を利用したうえ、異教徒の改宗まで目論むとか怖すぎます。
日本のバレンタインデーの始まり

始まりがなかなか物騒なバレンタインですが、次に日本のバレンタインデーの始まりについて書いていこうと思います。
日本のバレンタイン文化の始まりは諸説ありますが、一番有力な説は、1936年2月12日、洋菓子メーカーの神戸モロゾフが、チョコレート販売を促進させるため、外国人向けの英字新聞『ザ・ジャパン・アドバタイザー』に、愛する人へチョコレートを贈るという広告を掲載したことから始まったとされています。
この時はまだ女性から男性にという区別はなく、チョコレートの売り上げもあまりよくなかったようです。
女性から男性にチョコレートを贈る習慣はいつできたの?

バレンタインデーにチョコレートが売れ始めたのは、1970年代後半からのようです。
メリーチョコレートカムパニー(現在はロッテの傘下)が、「一年に一度、女性から愛を打ち明けていい日」というキャッチコピーで、女性からの支持を集めていき、バレンタインデーは女性から男性にチョコレートを贈るものという文化が根付いていきました。
バレンタインが日本に定着したのは女性にターゲットを絞って売り出したからなんですね。
まとめ
バレンタインの由来や起源が怖い理由と日本のバレンタインデーの始まりについて紹介させていただきました。
今では日本でのバレンタインデーはすっかり恋愛に関係なく、好きな相手やお世話になった人、友達や自分へのご褒美なんかでチョコレートやお菓子などを贈り合う楽しいイベントですが、始まりは意外ととんでもなかったですね。
冒頭にも注意書きをしましたが、バレンタインの由来や起源については諸説あるので、これが正しい歴史かというとそうではない可能性があるのですが、もし本当だったら当時の人々の思想や思惑なんかが伺い知れた内容になったのではないでしょうか。
この記事ではバレンタインの由来について書かせていただきましたが、バレンタインデーの由来があるならホワイトデーの由来もあるでしょ!
ということで、ホワイトデーの由来についても調べましたので、よろしければ読んでみてくださいね。
ここまで読んでいただきありがとうございました!
[…] […]